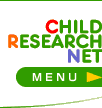|
●オックスフォード便り〜ディスレクシア研究室留学記〜 最終回
(2004年4月16日)
小山麻紀(オックスフォード大学生理学部博士課程)
BDA (The British Dyslexia Association) 国際会議に出席
3月27日〜30日までワーウィック大学(The University of Warwick, UK)で行われた英国ディスレクシア協会(The British Dyslexia Association。略してBDA)国際会議に参加してきました。この会議は3年に一度行われます。
BDAは、読み書き困難に苦しむ人々が彼らの持つ可能性を生かせるような世界を目指す、イギリス最大のディスレクア関係の団体です。主に以下の3つの部分で活動をしています。
1.ディスレクシアに理解を示し働きかけるよう学校に奨励する
2.犯罪に走るディスレクシア青少年の数を減らす
3.ディスレクシアの人々が、仕事において彼らの可能性を達成できるようにする
さて、今回の国際会議では、研究者だけでなく実践的にディスレクシア児童・大人を支援する側からも参加があった点が印象的でした。研究と実践の融合が、読み書き困難に苦しむ人々へ、より効果的な治療を提供できること実感しました。
*会議の詳細はこちらから。プログラムの覧にアクセスすると、各スピーカーの要約が掲載されています。
ディスレクシア原因についての様々な学説、そしてそれに伴う治療法に関する発表がありました。大切なことは、どんなタイプの読み書き困難を示すかによって、原因そして治療法が違ってくるということだと考えていますが、残念ながら、今回の会議ではアルファベットを使用する言語圏からの研究発表がほとんどでした。3年後の会議では、日本語・中国語のディスレクシアに関する研究が進み、言語の違いからくるディスレクシア症状の違いが明らかにされることと思います。
読み書きが困難=ディスレクシア とはいえない
日本語での発達性言語障害の本質は、まだまだ明確に解明されていません。
SLI(Specific language Impairment)という、特異性言語障害といわれる発達性言語障害があります。ディスレクシアと同じくSLIの原因も明確に把握されてはいませんが、主な症状として話し言葉、そして読み(読解力含む)に欠陥を示します。ディスレクシアとは違ったかたちで症状は表れるが、その障害を引き起こす根本的原因は同じではないかという研究者もいます*1。
しかしまずは、ディスレクシアとSLIという発達性言語障害が、児童の学業だけでなく社会生活にも暗い影を落とす現実を(その障害名を明確に識別することが難しくても)私たちが理解することが大切です。この言語障害を説明する説の一つは、ディスレクシア患者にも共通する音韻的プロセス問題がSLIを特徴づけると唱えています*2。
例えば、無意味綴りといわれる、本当の単語ではない音の一連を聞いた後同じように繰り返す音韻的ワーキングメモリーテスト(例:みけまさてろい)では、ディスレクシア患者のテスト結果は一般に比べると劣る傾向があります。それ以外にも、SLIの特徴的な欠陥は、シンタックス(統合法:句・節・文に内在する規則・文法)そしてセマンティックス(語や句・文の表す意味、その構造や体系)にもみられ、結果として読解力の低下につながることが多々あると推測されます。例えば、英語では、複数にする時に単語の最後に"s"をつける、動詞を過去形にする時に単語の最後に"ed"(規則的動詞)をつける等の語形変化を把握することに問題があるとされています。
しかしながら、英国の研究者の報告によると、ディスレクシアとSLIは両方とも音韻的プロセスに問題を示すが、基本的には違う発達性言語障害ではないかと示唆しています。*3 ディスレクシア児童の中には、他の言語スキルに頼ることにより、読みの困難を何とか克服できる場合もあるようですが、書字には問題が残ることが多いようです。一方、SLI児童 (動作性IQ100以上)の書字能力は通常レベルでも、年令とともに読みには著しく困難を覚える傾向にあります。彼らのシンタックス・セマンティクス能力の低さは、読解力の発達を長期的に深く妨げるようです。
日本語で読み書き困難を示す児童を、ディスレクシアかSLIに区別することは、それぞれの本質がまだ明確にわかっていないという事実、そして標準化された読み書きテストや検査テストがないことを考慮すると、容易なことではないと推測されます。しかしながら、ここで重要なことは、読み書き困難を示す子どもは、ディスレクシアだけでなく他の発達性言語障害をもつ子どもにもいるという事実です。
言語能力の発達と読み書き能力の発達は相互的に影響しあうと考えられていますので、その発達過程と原因機序の違いについての理解を深めることにより、それぞれの障害に最も効果的な検査法と治療法を提供できます。さらなる研究がそれぞれの障害に苦しむ児童に適切な指導をできるよう、私自身携わっていきたいと思います。
終わりに
明日4月17日からいよいよ国際ディスレクシアシンポジウムが始まります。これまで準備のために研究室にこもる日々でしたが、それももうすぐ終わり。5月以降は、博士課程の研究に集中し、何年後かには日本語でのディスレクシア研究の発展に貢献できたら嬉しく思います。
科学と教育の融合がさかんに唱えられる現在において、研究と実践的支援が、読み書き困難に苦しむ子どもたちに、新たな道をひらくことを心から願い、このエッセイを終わりたいと思います。
ありがとうございました。
==========================================================================
*1
例えば、P. Tallal。
*2
Prof. S.Gathercole。私の学士号のスーパーバイザーです!!
*3
Snowling, M. Bishop, D.V.M., and Stothard, S. E. (2000) Is preschool Language impairment a Risk Factor for dyslexia in Adolescence? (J. Child Psychol. Psychiat. Vo. 41, no. 5 pp 587-600)
==========================================================================
小山麻紀(こやままき)
大学卒業後、証券会社勤務を経て2000年に渡英。2003年ダーラム大学心理学部(ワーキングメモリー専攻)を卒業後、同年10月からオックスフォード大学生理学部博士課程に在籍中。
==========================================================================
本連載は今回で終了です。本連載の感想や小山さんへのメッセージはこちらから
|
|
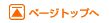
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
チャイルド・リサーチ・ネット(CRN)は、
ベネッセ教育総合研究所の支援のもと運営されています。 |
|
 |
|
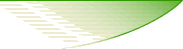 |
|
|