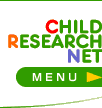|
●CRN英語版・おすすめサイト<9月編>
(2005年10月14日)
◆研究者からの投稿Articles by CRN Advisory Board Members
==========================================================================
Playthings That Do Things: A Young Kid's "Incredibles"!
Edith K. Ackermann, MIT, School of Architecture
==========================================================================
著者のアッカーマン女史は、なぜ子どもたちが動くおもちゃに夢中になるのか、また子どもたちが動くおもちゃで遊ぶ際に「認知、愛着、作用、制御」といった概念がどのように形成されるのかなどについて研究・レポートしています。
著者がアニメイツと文中で呼ぶ動くおもちゃとは子どもたちの遊び相手として開発された、ぜんまいや自動制御装置で自発的に動く玩具をさします。動かないおもちゃと違い、子どもたちの思い通りには動かないながらも、ものをコントロールするスリルを味わいことができるため、動くおもちゃは子どもたちの遊び心をくすぐります。発達心理学的にみるおもちゃのデザインにも言及しており、興味深い内容です。
◆米国ブラウン大学Child and Adolescent Behavior Letter5月号◆
==========================================================================
Keep Your Eye On...nicotine patch safe and effective for teens
==========================================================================
禁煙に用いるニコチンパッチとニコチンガムの安全性と効果を調べるために、13歳から17歳の若者120人を12週間にわたって調べた。
認知行動療法とニコチンパッチとニコチンガムを与えたグループ、その偽薬を与えたグループ、認知行動療法のみのグループの3群が比較された。実験期間と3ヶ月後の追跡調査の結果、偽パッチに比べ、本物のニコチンパッチのグループの禁煙成功率が明らかに高く、安全性にも問題がないようだったが、ニコチンガムには明らかな違いが見られなかった。
10代の多くが禁煙を試みて失敗しており、専門家の助けを求めているということです。
==========================================================================
New risk factors associated with suicide in adolescents
==========================================================================
米国疾病対策予防センターが1万人弱の高校生を対象に若者の自殺の危険因子に関する調査をしました。男子より女子の危険性が高い、人種間の違いは男子より女子に強く、白人に比べアジア系の女子に高い自殺傾向が見られる、うつ傾向の高いグループでは自殺を試みる危険性が5倍近くなるなど、いくつかの特徴が浮かび上がってきています。こうした特徴を踏まえての介入・予防プログラムを実施していくことが重要だと述べられています。
◆日本の高校生・大学生が綴る・Young Researchers’ Papers◆
==========================================================================
Korean Stars
==========================================================================
同志社国際高校の生徒さんの投稿から、「韓国のスター」。2002年のワールドカップと共に、近くて遠い国といわれた韓国をぐっと身近にさせてくれた韓国ブームについて述べています。過去の不幸な歴史を見つめながらも、今後の両国の関係に期待をよせる高校生の真摯な気持ちが伝わってきます。
==========================================================================
Ill-treatment
==========================================================================
同じく同志社国際高校の生徒さんのエッセイです。痛ましい児童虐待のニュースが続いています。原因の分析にあたっては日本人に特徴的な考え方、態度も影響しているのではないかと述べていて、大変考えさせられます。
==========================================================================
School Trips Save the World!?
==========================================================================
小学校の修学旅行で広島、中学校で長崎、高校で沖縄を訪れ、戦争の悲惨さに衝撃を受けた筆者は、本を読んだり、体験者から話を聞いたりして多くのことを学びます。イラク戦争にからんで、日米の関係に疑問を投げかけながら政治家もこうした修学旅行に加わり、再度平和について考えてほしいと主張しています。
◆研究者・実践者によるエッセーMonthly Articles on Children◆
==========================================================================
Children within an Internationalizing Environment
Judit Hidasi, Professor, Kanda University of International Studies
==========================================================================
9月3日(土)、4日(日)に、「多文化社会と子どもたち―未来をつくる共生と支援―」をテーマに行われた第2回子ども学会議で、神田外語大学国際コミュニケーション学科のヒダシ・ユディット教授が発表した講演、「多文化と価値の衝突」の内容をダイジェスト版にして掲載しました。
数十年前と比べ、日本は多文化社会へと大きく変容しています。その背景、社会的な要因、子どもたちの行動パターンの変化、教育事情、変化によって起こりうる衝突などについて簡潔にまとめられています。
==========================================================================
Ritalin - A Corresponding Issue in Terms of Cultural Diversity
Ryoko Matsumoto, M.Ed. in School Psychology and Counseling Education, College of William and Mary
==========================================================================
2005年度のチャイルド・サイエンス懸賞エッセイに入賞した、松本亮子さんからの寄稿です。
心理学専攻でアメリカに留学中の松本さんが、カウンセラーとしてインターンで働いていた際、学校の医務室でリタリンを処方してもらうために子どもたちが列をなしているのを見て驚いたというエピソードから始まるエッセイ。リタリンは、アメリカではADHDの治療薬として広く普及し、その消費量はここ数年で7倍にも急増していますが、日本では認可さえされていません。なぜリタリンがアメリカで普及するのか、日米の文化の違いに注目し、その理由を探るレポートです。
|
|
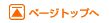
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
チャイルド・リサーチ・ネット(CRN)は、
ベネッセ教育総合研究所の支援のもと運営されています。 |
|
 |
|
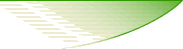 |
|
|