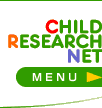|
●CRN英語版・おすすめサイト<11月編>
(2005年12月9日)
◆米国ブラウン大学Child and Adolescent Behavior Letter7月号◆
==========================================================================
How do teens regard peers with psychiatric disorders?
==========================================================================
近頃行われた調査によると、高校生はアルコールを乱用している仲間や精神疾患に苦しんでいる仲間を強く白眼視していることがわかった。肉体的な問題をかかえている人に比べて、精神的な問題を抱えている人にきびしい目をむける大人の傾向と一致するものである。
同じ精神疾患でも脳腫瘍を原因とするものに対しては、悪い印象が薄れ、危険を感じるよりも助けたいと感じている。また、大人は精神疾患を抱えた人と接することによって、差別感情を弱めていくが、若者は逆に強めている傾向も明らかになった。研究者たちは、こうした調査をもとに、偏見を持ち続けることがないように精神に問題を抱える人たちに対する差別意識をなくしていく若い人々向けのプログラムを開発し、実施していく必要があると述べている。
◆研究者からの投稿 Research Papers
==========================================================================
Re-conceptualizing Early Childhood Education - From Asian View
Jiaxiong Zhu, Institute of Early Childhood Education, East China Normal University
==========================================================================
華東師範大学(中国・上海)の朱家雄教授が、アジア、主に中国における幼児教育の理想のあり方について述べたレポートです。欧米の従来の幼児教育をそのままアジアに取り入れるのではなく、アジアの文化、思想に沿った幼児教育を考えていく必要があると述べられています。毎年、アメリカで開催される幼児教育のあり方を問うシンポジウム"Reconceptualizing Early Childhood Education" において朱教授が2003年に発表した内容をまとめたものです。
==========================================================================
New Fathers Take Parental Leave- Case Studies of Six Couples in Canada
Marlene Ritchie, B.S., M.N.
==========================================================================
欧米では子育て中の父親が育児休暇を取得する件数が年々増えてきています。本論は、カナダの子育て中のカップル6組にインタビューした内容をケーススタディとしてまとめてレポートしたものです。
両親ともに育児休暇を取ることによって子どもを見る目、夫婦関係が格段に変化した、親として自信がついたなどの興味深い内容があります。 父親の育休取得の一番の悩みとして、企業や自治体からのサポートがあるとはいえ、世帯収入が一時的に減るという点が挙げられていますが、家族として貴重な時間を持てた事には全ての夫婦が大満足であると回答しています。
◆研究者・実践者によるエッセー Monthly Articles on Children◆
==========================================================================
Mickey Mouse Views
Hillel Weintraub, Traveling Writer, Designer, Learner
==========================================================================
香港に新しくオープンしたディズニーのテーマパークについて、ヒレル氏が感じたことを綴るエッセイです。 アメリカで、ミッキーマウスという単語は、有名なネズミのキャラクターを指す以外に、口語で「たいしたことのない様子」や「中身がない様子」を表すのだそうです。 たとえば、大学の簡単なクラスは「ミッキーマウス・クラス」、適当な答えは「ミッキーマウス・アンサー」というように。ヒレル氏は、ディズニーに代表される巨大なアメリカ企業は、テーマパーク建設や関連商品の輸出だけでは終わらせず、香港にアメリカ式「ミッキーマウス・ライフスタイル」も浸透させるだろうと延べ、子ども達に安易に夢を売るディズニーに対し、批判的な意見を述べています。
==========================================================================
Children in Multilingual World
Manami Nishida, CRN Staff
==========================================================================
多文化が共存する移民の国、オーストラリアで幼児教育を学び、今年の春に大学を卒業したばかりのCRNスタッフが移民の子どもが外国語を学ぶプロセスについて自身の幼稚園での実習体験をもとに感じたことを綴るエッセイです。家庭では母語を、集団生活では英語を話さなくてはならない環境に置かれる子ども達の言語習得サポートは、多文化保育園における重要な課題です。日本の国際化が進む中、海外の多文化保育園の実践内容を知り、日本でも取り入れていくことが、今後重要になるだろうと意見を述べています。
◆日本の高校生・大学生が綴る Young Researchers’ Papers◆
==========================================================================
Looking for Myself, Mayuko
==========================================================================
同志社国際高校の生徒さんの作品から。イタリア生まれのオーストラリア人高校生が自己のアイデンティティーを求めていく過程を描いた物語"Looking for Alibrandi"を読んでのエッセイです。ドイツで生まれ、小学生のときに日本にやってきた筆者が自身の経験や様々な国からドイツにやってきた当時のクラスメートの話から、自分がどのように今の自分にいたっているか、自己のアイデンティティーを探っています。
|
|
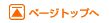
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
チャイルド・リサーチ・ネット(CRN)は、
ベネッセ教育総合研究所の支援のもと運営されています。 |
|
 |
|
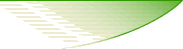 |
|
|