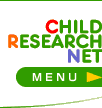|
●CRN英語版・おすすめサイト<2月編>
(2006年3月3日)
◆研究者からの投稿Research Papers
==========================================================================
Integrating Children Who Speak a Foreign Language into English Nursery Schools in Toronto, Canada
Marlene Ritchie, B.S., M.N., International Educator
==========================================================================
保育園で外国語を話す移民の子どもを受け入れるための実践内容をレポートした寄稿です。
カナダのトロントでは、12歳までの子どもの10人に4人が移民の子どもであるため、保育士は受け入れに慣れているのだそうです。英語環境の保育園に移民の子どもたちが慣れるために大切なことは、子どもが慣れない保育園で居心地よくなるように、子どものネイティブ言語や育った習慣などを園に持ち込めるような環境を整えることだそうです。二ヶ国語を話す子どもの場合は、絵を見ながら二つの言語で説明し、単語同士が同じものを指すことを丁寧に教えてたりすることで、ネイティブ言語を媒体にし、より英語をスピーディに学ぶことができるのだそうです。
◆米国ブラウン大学Child and Adolescent Behavior Letter10月号◆
==========================================================================
Imus and Autism
==========================================================================
イムス(Don Imus )はアメリカで人気のラジオトーク番組「Imus in the Morning」のホストであり、辛らつな物言いと行動力、数々のチャリティー活動から絶大な人気と影響力を誇っているようです。
今月のエディターズ・コメンタリーでは、編集長のグレゴリー・フリッツがこの番組のひそかなファンであることを告白しています。子どもの問題に関心を持っているイムスは、近頃、自閉症について、ワクチンの保存剤であるチメロサールに含まれる水銀が原因であるとの見解を支持しました。この水銀原因説はワクチンの不安を無用に煽り、体内から水銀を除去するための“自閉症治療”、水銀キレート療法では死者も出ています。いつの時代にも、原因の分からないものに対する断定的なはっきりとした物言いは大衆の心をつかみ、惑わせます。現代のカリスマであるイムスの影響力は大きく、人々の思考を奪い、科学的な根拠から目をそらせるものです。筆者はこうした現象を憂え、警告を発しています。
◆研究者・実践者によるエッセーMonthly Articles on Children◆
==========================================================================
Culture and Influence
Rebecca Cataldi, Former CRN Staff
==========================================================================
半年ぶりに来日した元CRNスタッフのレベッカさんが、日本で滞在中に感じたことをエッセイにした寄稿です。レベッカさんは、日本とアメリカの文化が今までになくお互いに影響を与え合っていると感じたようです。アメリカではスシ人気がすっかり外食産業に定着したり、子どもはミッキーマウスよりもポケモンやスーパーマリオを欲しがったり、これまでにない勢いで、日本のポップカルチャーが「かっこいいもの」、「かわいいもの」としてアメリカの現代っ子の間で人気を得ているのだそうです。レベッカさんは若者がお互いの文化に良いイメージを持ち交流を進めることが、国同士で良い関係を築くことに役立つことを期待しているそうです。
==========================================================================
Gifts from the Logo Culture of Learning
Hillel Weintraub, Writer, Designer, Former Professor of Future University -
Hakodate
==========================================================================
セイモア・パパート教授が発明した子どもたちに新しい技術をコントロールする力を身に付けさせようとする最初でかつ最重要な活動であるロゴ・コンピュータ言語とその教育哲学の意義を改めて考えたヒレル氏。間違いをおかし混乱することが、ものごとを関連づけて論理的に考える過程を学び、ものごとの理解を深める上で非常に重要だとするロゴの教育哲学に感銘を受けたのだそうです。教育をする側もされる側もこの哲学から学ぶことは多いだろうと述べています。
◆英語で読む・日本の子どもとメディア◆
==========================================================================
A Popular Portal Site among Youth in Japan, Cafesta
-Finding out What Many Teens are Doing on an Interactive Web Community
Shinya Kawakami, CRN researcher
==========================================================================
「子ども未来紀行」より、「子どもが集うコミュニティサイト・Cafestaとは?」を英訳しました。マイホームページ、チャット、コミュニティサイトなど英語ではどう説明するんでしょうね。
◆英語で読む・子育て本◆
==========================================================================
The Human Science of Mother and Child:Disturbance of Mother-and-Child Relationship - 2
Noboru Kobayashi, M.D. ,CRN Director
==========================================================================
小林登文庫「新・こどもは未来である」より、「母と子の人間関係が乱れる−2」を英訳しました。母親の愛情にめぐまれない子どもは、ときによっては身長がのびないなど成長に影響が出るそうです。愛情という目に見えないものが成長や発達に影響を与えるとは不思議な話ですね。
|
|
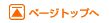
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
チャイルド・リサーチ・ネット(CRN)は、
ベネッセ教育総合研究所の支援のもと運営されています。 |
|
 |
|
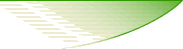 |
|
|