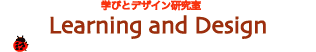
コミュニケーションの基本って?
人やモノやできごととのかかわりによる経験の再構成が、学びのプロセスであるとするならば、よりゆたかなかかわりの場を用意することがワークショップには求められる。ワークショップのテーマが決まれば、具体的にデザインするのは、どのようなかかわり─コミュニケーションを通してそのテーマへ近づいていくかということになる。すなわち、ワークショップのデザインについて考えるということは、ある状況におけるコミュニケーションのあり方について考えることであるとも言えるだろう。
コミュニケーションについて考えていると、子どもの振る舞いにハッとさせられることがしばしばある。ノンちゃんは1歳半。普段は離れて暮らしている大好きなカコちゃん(おばあちゃん)と、今日は久しぶりに会ってお食事。いつもは、何をするのでもママでなければイヤイヤッなのに、スプーンにごはんをすくってはカコちゃんと目を合わせてニッコリ、一口食べてはまた目を合わせてニッコリだ。そんなノンちゃんの様子を見ていると、あることに気がつく。ノンちゃんは何かをするたびに、カコちゃんに見てもらうのを待っている。ごはんをすくったスプーンを持ったまま、自分のほうを見てくれるのを真剣な面もちで待ち、カコちゃんにニッコリしてもらってはじめて表情を緩めてスプーンを口に運ぶ。まだオシャベリは苦手なので目をわせてニッコリし合うだけなのだけれど、その「目を合わせる」「ニッコリし合う」を繰り返して、そのたびに「できたよ」というよろこびをカコちゃんと確認し合っているようだ。
群馬県立あさひ養護学校(群馬県桐生市)で開催された「障害児のためのメディア・アート・ワークショップ」で、「たのしさ倍増ケイカク〜コミュニケーションの軌跡をまとう」を大木友梨子さん(e-とぴあ・かがわ)と一緒に担当した。「たのしさ倍増ケイカク」とは、「よろこびは伝え合うと倍うれしくなる」ということをワークショップを通してやってみようというもの。「コミュニケーションの軌跡をまとう」という手法は、昨年の苅宿俊文先生(NPO学習環境デザイン工房/大東文化大学)のワークショップ「Tシャツではなそうよ、ねぇ」からアイディアをいただいた。すなわち、このワークショップは、楽しさやうれしさを伝え合うというやりとりを重ね、そのコミュニケーションの軌跡を目にみえるかたちで身体にあらわしていくというもの。
参加者もスタッフもみな白いポンチョを着て、色とりどりのセロハン片が入った透明のポシェットを首からさげている(写真1)。今日ここで出会った人たちと、このポンチョとセロハンを使ってやりとりする。側にいる人に声をかけて、「さっきのワークショップ楽しかったね」と感想を伝えながらポシェットの中のセロハン片を1枚相手のポンチョに貼りつける(写真2)。セロハンはいわば自分の気持ちを乗せた媒介物だ。「楽しかったね」という気持ちは、胸のポシェットからひらひらと飛び出して相手の身体の上に届けられる。セロハンを貼ってもらった人は、次は自分のポシェットから2枚のセロハンを出してさっきの言葉に応えながら相手に貼る。ひとつ伝えると倍になって返ってくるという仕組みが目にみえるかたちで身体に残されていき、声をかけあうたびにポンチョは色とりどりのセロハンでうめられていく。
このワークショップの参加者には会話することが困難な子もいた。スタッフの大学生たちは、子どもたちとどのようにやりとりすればいいのかということについて心配していた。会話が成立しないのならそれはコミュニケーションができないということなの?と彼らは気にしていたのだ。議論を重ねるうちに、「手をぎゅっとにぎるのもコミュニケーションだよね」「目が合うだけでもいいんじゃない?」と、それまでしばられていた「言葉のやりとり」を越えたコミュニケーションのあり方にみんなが気づきはじめた。もしかしたら、うまく言葉にならないかもしれない。でも笑顔でセロハンを渡せばかかわろうとする心が伝わり、お返しとして2枚のセロハンを受け取ることができれば、そのコミュニケーションは成立したことになる、と。
ここでは、確実にセロハンを渡すことができ、それを受け取ってセロハンを倍返ししてくれる相手がいることが重要になってくる。ワークショップの会場にはたくさんの人がいる。しかし不特定多数にむかって言葉を発してもポシェットのセロハンをあげることも、お返しとして自分のポンチョにセロハンをはってもらうこともない。ここでは、「みなさーん」と声をはりあげるよりも、ひとりときちんと向かい合うことが求められている。「みんな」ではなく、「ひとり一人」とかかわることが。誰かひとりに自分の気持ちを乗せたセロハンを渡すことで、その気持ちを受け取ったという返事の乗ったセロハンがかえってくる。それを繰り返すことで、ポンチョにはひとつ、ふたつとセロハン片が増えていく。ひとり一人がきちんと向かい合えば、ただ目を合わせてニッコリするだけでも、コミュニケーションが成立して、よろこびが倍増する。たしかに、まだ1歳半のノンちゃんだって相手と目が合うまで待っていた。コミュニケーションの基本は、こういうところにあるのかもしれない。
 |
 |
 |
| 写真1: 参加者はみな白いポンチョを着てセロハン片の入ったポシェットをかけています。 |
写真2: やりとりしながら、セロハン片をたがいに貼り合います。 |
写真3: みんなのポンチョをつなげて、コミュニケーションの軌跡であるセロハンの光を鑑賞しました。 |
あさひdeアート2004 (ポスター画)
Copyright(c), Child Research Net, All rights reserved.